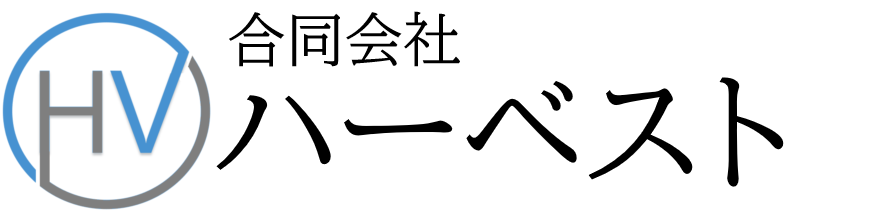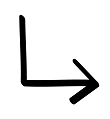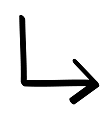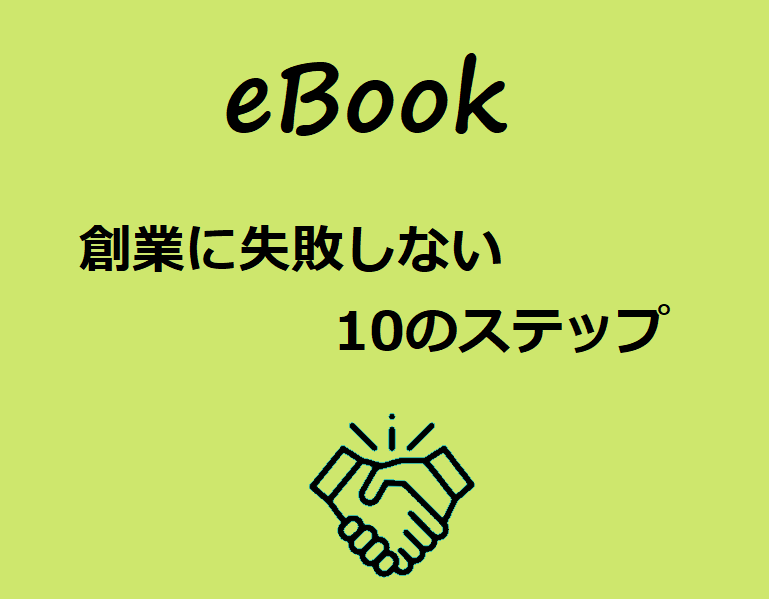❾ デジタルに始めれば司法書士も税理士もいらない
会社経営のわずらわしさは税務と経理にある?
1人で会社を始めたあなたは、本業の仕事(例えば、料理を作るとか、ペットをトリミングするとか、お花を仕入れて売るとか、経営コンサルをするとか・・・)に加えて、その仕事を得るためのマーケティングや営業の活動をしなければなりません。毎日のようにブログやSNSを更新し、関係先にチラシを配りにいく・・・これだけで手一杯!
いえいえ。さらに毎日の売上や支出を記帳し、毎月あなた自身への給料から税金と社会保険を天引きし、翌月それを納付し、年末には年末調整、事業年度が終われば決算報告と法人税等の確定申告といった具合に、あなたは少なくとも「1人三役」をこなさなければならないのです。
「そんなの到底無理だから、税務と経理は税理士に委託しよう!」
あなたがそう考えても、無理はありません。
小さく始める創業には司法書士と税理士が過大な負担です
しかし、私はこう思います。
- 1人合同会社など小さく始める創業には、外部委託は負担が大きすぎる
- 税務と経理のわずらわしさは、デジタルで大幅に軽減される
- 自己管理の仕組みをうまく作れば、「習慣づけること」が可能
まず1番目の負担の問題が大きいですね。
業界の相場情報に詳しいアイミツによれば、税理士の業務別相場は次のようになっています。
| 項目 | 個人 | 法人 |
| 記帳代行料 | 月額6,000円~1.5万円 | 月額7,000円〜3万円 |
| 顧問料 | 月額1.3万円~3万円 | 月額1.5万円〜5万円 |
| 申告代行料 | 月額7.5万円〜15万円 | 月額10万円〜23.5万円 |
”上記をすべて含めてトータルの費用に換算した場合、平均費用は月額7万7,500円。
年次の決算処理と税務調査立ち合いなどの料金を含めて年間平均123万円です。”(アイミツより引用)
これは平均値なので、創業したての小さな会社では、ここまで高くはありません。顧問契約はしないとすれば、毎月の記帳代行に1万円くらい、確定申告の代行に10~20万円、合わせて年間20~30万円くらいは最低でもかかります。
この金額をどう考えるかですが、創業初年度の20~30万円の負担は大きくありませんか?実際の事業月数が6カ月しかなくても、申告代行は同額ですから、創業初年度の粗利が6カ月で60万円(月額10万円)あったとすると、その半分近くが税理士への支払いで消えてしまうことになります!
法人の設立登記について詳しくはこちら
創業10のステップ深掘り編 設立登記の電子申請
税務、労務、経理のインフラをデジタルに構築する
2番目のポイントですが、デジタルつまり経理ソフトや申告書作成ソフトを導入すれば、この経費が大幅に削減できます。
経理ソフトも申告書作成ソフトも、それぞれ年間で2万円くらいです。合わせて4万円。これを使いこなせれば、あなたは「1人3役」が可能となります。
ちなみに、触れなかった司法書士ですが、司法書士は登記の専門家で、法人設立登記の時に委託する人が多いです。相場は、合同会社で10万円くらいですね(税理士や行政書士に任せることもできます)。
法人登記申請は、法務省の「登記・供託ねっと」サービスを使えば、「事実上」無料でできます。(*「事実上」の意味は、後ほど説明します)
税務・労務・経理のデジタルインフラ」の意味
インフラというのは、「基盤」というような意味ですし、またシステムという意味でもあります。下の図が、「税務・労務・経理のデジタルインフラ」を表しています。
毎日のように出てくる売上や費用(そこには原材料費や営業費用などとともに給与が含まれます)を、月に一回せきとめて整理し、それを行政機関が発行している、e-Tax(イータックス)、eLTAX(エルタックス)、eGov(イーガブ)というソフトを使って、住民税は市区町村と都道府県に、所得税は税務署に申告し、納付します。法人口座からは税額や保険料が自動的に引き落とされます。
そして年末には、毎月「概算」で出していた所得税を、もう一度正確に計算し直して、差額を1月の給与に反映します。そして年間の給与支払の合算を、市区町村に報告します(7月には年金事務所にも報告します)。年度末には決算報告書を作り、その他のデータと合わせて法人税などに関する確定申告書を作成し、e-Tax、eLTAXで送ります。法人税などが口座から引き落とされます。
こういう決まり切ったルーチンの作業を、デジタルベースでつつがなく行える仕組みを作って置けば、税理士は必要ありません。この仕組みを「税務・労務・経理のデジタルインフラ」と呼んでいるわけです。
税金と社会保険のインフラ構築について詳しくはこちら
税理士のいらない電子納付の準備 税理士のいらない電子納付の実際
インフラを使いこなすことを習慣化する
3番目の論点は、経理ソフトなどを使いこなせるかどうかは、知識と習慣づけに依存するという点です。知識というのは、そもそもの税金や社会保険の仕組みについて知ることと、ソフトの操作方法を理解するということを意味しています。これらは、「ゼロから始めて経営を軌道に乗せるまでのワンストップの手引」である、このeBookとStepガイドシリーズを読んでいただければ、そうした知識は間違いなく身に付けることができます。
課題は、「習慣づけ」の方でしょう。家事もフィットネスも、必要性とやり方は分かっていても、習慣づけが難しいですよね!
料理が一番いい例なんですが、料理上手(あるいはプロ)のキッチンは、いつもきちんと整理されています。素材は冷蔵庫・冷凍庫に、調味料はワゴンや棚の上に、調理器具はテーブルの前やコンロの横に、種類や用途に合わせてすぐに使えるように配置されています。そしていつもきれいにメンテナンスされています。
そんなキッチンと同じように、デジタルには、デジタル独特の整理の仕方があって、それを守れば、デジタルルーチンは、とてもやりやすくなります。習慣化できないのは、めんどうくさいからであって、そのわずらわしさが激減すれば、作業はむしろ楽しくなります。料理のように!
デジタル独特の整理のコツは、
アカウントとフォルダーのクラスター化です!
デジタル作業の整理の仕方のポイントは、バーチャルな空間をイメージすることです。
あなたがお花屋さんだとして、自宅の道路に面した部分にお花を展示して、外から入ってくるお客さんに花を売ります。ここを「顧客関係」というクラスター(*コロナのおかげで、このことばが普及しましたね。集団とか集合という意味ですが、ここでは部屋だと考えてもらっていいです)として、記号Cを与えます。
Cクラスターの裏側に、お花を加工する作業場があり、ここを「ビジネスのガレージ」と名づけ、記号Bを与えます。
CとBの横に、家族が普段の生活に使っている部屋の集まりがあって、ここを「プライベート」と名づけ、記号Pを与えます。
それぞれのクラスター(部屋)には、電気、ガス、水道というインフラが通っていますね。バーチャル空間でも、「税務のインフラ」というクラスターが、CとBに共通してあります。記号Tです。
そして、C、B、Tというクラスター構造(つまり間取りです)を持った部屋を、あなたはショッピングモールに借りています。クラウドサービスのたとえです。
Googleとか、Adobeとか、メールサービス、Webサイト、e-TaxやeLTAX、銀行のインターネットバンキング・・・これら全てが、クラウドサービスです。
そして、あなたはそれぞれのサービス(ショッピングモール)に、Cの部屋、Bの部屋、Tの部屋があって、部屋番号があり、そこに入るカギを持っています。そうです。部屋番号がアカウント、カギがパスワードです。
次の図は、リアル(自宅兼店舗)とバーチャル(クラウドサービス)に共通の、クラスター構造を例示してみたものです。P(プライベート)を除いて、パスワードを同じものにしています。つまり合鍵です。アカウントは実際にはかなりの数になるので、パスワードを全部異なるものにするというのは現実的ではありません。むしろ共通にして、定期的に変更したほうがセキュリティーにもプラスだと思います。
| 記号 | クラスター | アカウント | パスワード |
| C | 顧客関係 | service@harvest.org | 1234@abcd |
| B | ビジネスのガレージ | harvestlaw@gmail.com | 1234@abcd |
| T | 税務インフラ | kishi@harvest.jp | 1234@abcd |
| P | プライべート | xxxx@gmail.com | xxxxxxxx |
そして、バーチャルと同じクラスター構造を、あなたが仕事に使うパソコンにも反映させます。次の図は、非常に単純化した、抽象的な構造ですが、パソコンのブラウザ、メール、カレンダー、ドライブ(クラウド上のストレージ保存場所)、デスクトップ、そしてパソコンに外付けしたハードデスクメモリーをイメージしています。
プライベートは、できれば別のパソコンか、スマートフォンに限った方がいいでしょう。ビジネスとの共有は、色々な意味で危険です。
これが、料理上手のキッチン整理法に対応する、デジタル経営のアカウントとフォルダー整理法なのです。このようにして、顧客とのコミュニケーションとそのデータ、ビジネス全体を構築し管理するデータ、そして税務、労務、経理に関するデーターを、C、T、Bのクラスター構造で整理し、
互いに関連づけるアルゴリズム(論理)を作れば、
「税務、労務、経理のデジタルインフラ」の管理操作を習慣づけることは、半年もすればできるようになるはずです。
e-Bookで読める、今だから特典
● ご記入いただいたメールアドレスにダウンロードURLをお送りします。
● e-Bookは、総合編の他、深堀編やStepガイドは分野別に分かれていますのでリストから選んで、お申しつけください。